あれ?今年の節分は2月2日?3日じゃないの?
節分といえば2月3日というイメージがありますが、2025年の節分は2月2日になります。
実は、この日付の変動には地球の公転周期が関係しているのです。
本記事では、節分の日付が変わる理由や仕組みについて、分かりやすく解説していきます!
これを読めば、節分の仕組みをしっかり理解できますよ。
それでは、さっそく見ていきましょう!
【節分】2月2日になる理由を徹底解説!
節分といえば2月3日が定番のイメージですが、2025年の節分は2月2日になります。
なぜ日付が変わることがあるのでしょうか?
その理由を詳しく解説していきます!
① 節分の本来の意味とは?
節分とは「季節を分ける」という意味を持つ言葉です。
もともとは立春・立夏・立秋・立冬、それぞれの前日を指していましたが、現在では特に「立春の前日」のことを指すようになりました。
立春は旧暦において一年の始まりと考えられていたため、節分は「新年の前日」のような意味合いを持っていました。
そのため、節分には「邪気を払う」「新しい年を迎えるための行事」として、豆まきなどの風習が生まれたのです。
② 節分の日付が変わる理由
節分の日付が変わるのは、地球の公転周期と暦のズレが原因です。
地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間は、約365.2422日で、暦の1年(365日)とは少しずれています。
このズレを調整するために、うるう年(4年に1度、366日になる年)が設けられていますが、それでも微妙なズレが発生し続けます。
このため、立春の日が毎年少しずつ変動し、その影響で節分の日付も変わることがあるのです。
③ 2025年の節分はなぜ2月2日なのか?
2025年の立春は2月3日になります。
そのため、その前日である節分は2月2日となるのです。
実は、2021年にも節分が2月2日になっていました。
このときは124年ぶりの珍しい出来事として話題になりましたが、今後は4年ごとに2月2日になるサイクルが続く見込みです。
④ 2月2日になる年と、3日に戻る年の違い
節分が2月2日になるのは、地球の公転周期によるズレの影響で、立春が1日早まるタイミングにあたる年です。
2021年以降、4年ごとに2月2日になるパターンが続くと予測されています。
ただ、うるう年の翌年の節分が必ずしも2月2日になるというわけではありません。
実際、2017年までは,うるう年の翌年であっても立春を迎えるタイミングが2月4日(例えば2017年は2月4日0:34)でした。
ですが、2021年は立春のタイミングが2月3日23:59になり、ギリギリで2月3日になったので、節分が2月2日となりました。
そして2025年の立春は2月3日23:10で、すこしずつ時刻をずらしながらも、当分の間はうるう年の翌年の節分は2月2日になることが予測されるというわけです。
近年の立春と節分
(Wikipedia – 立春 から引用)
| 年 | 立春(日本時間) | 節分 |
|---|---|---|
| 2017年 | 2月4日00:34 | 2月3日 |
| 2018年 | 2月4日06:28 | 2月3日 |
| 2019年 | 2月4日12:14 | 2月3日 |
| 2020年 | 2月4日18:03 | 2月3日 |
| 2021年 | 2月3日23:59 | 2月2日 |
| 2022年 | 2月4日05:51 | 2月3日 |
| 2023年 | 2月4日11:42 | 2月3日 |
| 2024年 | 2月4日17:27 | 2月3日 |
| 2025年 | 2月3日23:10 | 2月2日 |
【節分】歴史と由来
節分の由来は、古くは中国から伝わったとされる宮中行事「追儺(ついな)」に遡ります。
また、日本独自の風習として「鬼は外、福は内」という豆まきの文化が生まれました。
ここでは、節分の歴史を詳しく見ていきましょう!
① 節分の起源は中国の風習?
節分のルーツは、中国の「追儺(ついな)」と呼ばれる厄払いの儀式にあるとされています。
追儺は、古代中国で行われていた「疫病や災いを払う儀式」で、これが日本に伝わり、宮中で行われるようになりました。
平安時代には、宮中で大規模な追儺の儀式が行われ、鬼を追い払う役目を持つ「方相氏(ほうそうし)」が活躍していました。
② 平安時代から続く宮中行事「追儺(ついな)」とは?
平安時代の宮中では、鬼の面をかぶった役人が、矛や盾を持って宮廷内を駆け巡り、邪気を払う「追儺」の儀式が行われていました。
この儀式が、庶民の間に広まり、鬼を追い払う行事として「節分」に定着していったのです。
③ なぜ「鬼は外、福は内」と言うのか?
豆まきの掛け声「鬼は外、福は内」は、邪気を払い、幸福を呼び込む意味があります。
これは「鬼(悪霊)を追い払い、福を家の中に呼び込む」という考えに基づいています。
また、鬼という存在は、単なる妖怪ではなく、病気や災害などの厄災を象徴するものでした。
これを追い払うために豆をまく習慣が生まれたのです。
④ 節分と「年越し」の関係
昔の日本では、立春を新年の始まりとする考え方がありました。
そのため、節分は「旧暦の大晦日」のような意味を持ち、年越しの厄払いとして行われていたのです。
【節分】まとめ
節分が2月2日になる理由は、地球の公転周期と暦のズレによるものです。
立春の前日が節分と決まっているため、4年ごとに2月2日になることがあります。
2025年の節分が2月2日なのは、2024年がうるう年にあたり、立春の日が1日早まるためです。
今後もしばらくは4年ごとに2月2日の節分が訪れることが予想されています。
また、節分はもともと「季節の変わり目に邪気を払う行事」として始まりました。
宮中行事「追儺(ついな)」がルーツとされ、平安時代から続く伝統行事です。
現在では「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆をまく習慣が根付いています。
このように、節分は単なる年中行事ではなく、古くからの風習や歴史が詰まった特別な日です。
今年の節分は、ぜひ由来を意識しながら楽しんでみてくださいね!
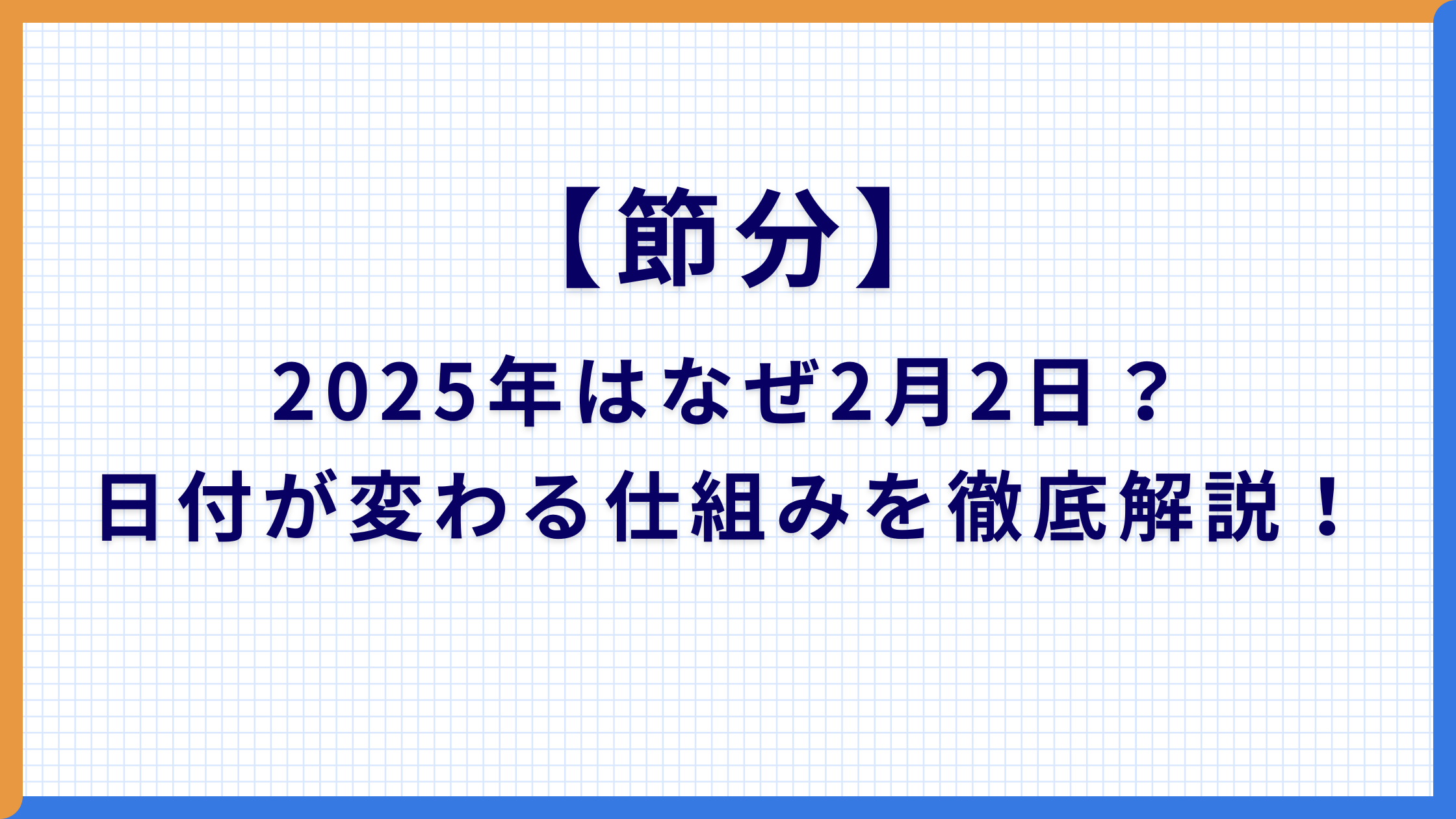
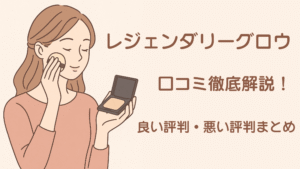
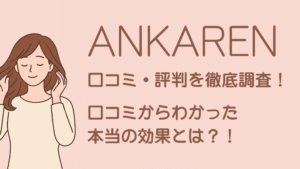
コメント